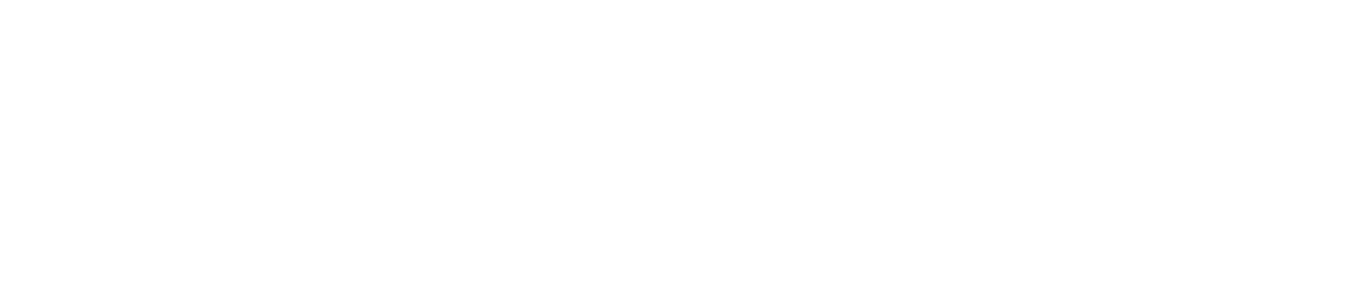政策研究大学院大学 名誉教授 大野健一
2025 年7月15日
GKM 社は、ベトナム企業のレベルアップ方法を独自に開発し、実践に移すコンサルタント会社である。グェン・ダン・ミン(Nguyen Dang Minh)博士がハノイで 2015 年に創設した。同氏は日本で工学を学び、東大で修士、名大で博士を取得、愛知県のトヨタ本社で生産管理を担当し、そのあと帰国してこの会社をつくった。彼の特徴は、日本で学んだモデルをそのまま移植するのではなく、ベトナムの風土・文化にあった指導・訓練法を、日本を参照しながらも新たに開発する点にある。彼は現実に立脚した研究者かつ実践者であり、有能な知日産業人材でもある。私が彼に初めて会ったのは2008年だった。それ以来、関心をもって彼の方法と活動を見守っている。

ミン氏は、同じく日本への留学経験がある奥さんのザンさんや弟のトアンさん、そして彼の実践理論に共感する有志たちとともに、グランドデザインをもって会社を運営している。企業経営者にマインドセットやファイネスト・マネジメント(The Made in Vietnam Finest Management)を教えるCEO コース、一般人に家庭での子供のしつけを教えるコースを毎年数回ずつ実施。聴講者からは、彼の考え方に共鳴し、うちの会社をぜひ指導してほしいという社長も出てきている。そのコンサル業務では、ミン氏や彼のチームが個別企業を定期的に訪問し、新理論を駆使して企業文化を変革し、実績をあげている。いっぽうザンさんは、家庭訪問を通じて家での5S やカイゼンを教える。また教育方法を改革するプログラムもある。現在の活動や将来の計画・夢はたくさんあるようで、しかも修正・追加があり、私はすべてを把握しきれていない。

大野健一教授、グエン・ダン・ミン准教授博士、そしてWindtechテクノロジー株式会社の経営陣によるWindtech訪問中の様子。
GKM社の方法論
私は長年、彼の説明を聞き、著書を読み、企業訪問もさせてもらった。彼の方法論の大筋はわかったが、詳細を完全に理解することはできなかった。それは、詳細は企業秘密だったこと、方法を開発する試行錯誤の間は発表したくなかったこと、私も企業指導の現場をつぶさに観察する機会はなかったことによる。だがGKM社は今年で設立 10 周年を迎え、企業指導の成果も明確になったので、いまは方法論を公開したいとミン氏は私に語った。彼の説明は私にとってまだ必ずしも明快とはいえないのだが、私なりに総合すると、次のような方法論となる。
第1に、ベトナム人は日本人と異なること、ゆえにベトナム人がものづくりをきちんと実践するには正しいマインドセット(Tam The)が必要であり、これがないところにカイゼンツールなどを個別に導入しても効果がないという前提から出発する。日本のコピーではだめなのである。これを企業の現場でどう教えるかはその場に立ち会わないかぎり十分理解できないだろうが、これまで私が聞いてきたところから判断するに、その手順は次のようなものと思われる:①社長のコミットメントを確認し、GKM 社の方法を現場で貫徹する許可を得る(これがなければ開始しない)、②会社のすべての部署の部長・課長を一堂に集め、方法に関する講義と討論を重ねる、③最初は反対者・懐疑論が多くても、回数を重ねるうちに「そこまでいうなら一度やってみよう」という意見が大勢となり、残る反対者を排除・左遷する、④部長・課長はそれぞれの部署に戻り、すべての従業員を動員して、各工程の標準作業手順書(SOP)を作成させる。その作業をGKM社が指導し、従業員の自発的参加を推進する。

大野健一教授、グエン・ダン・ミン准教授博士、そしてWindtechテクノロジー株式会社の経営陣によるWindtech訪問中の様子。
以上は、日系企業や JICA 専門家が5S やカイゼンを教えるやり方とは全く違っている。摩擦やテンションをかなり生みそうなやりかたで、全社を巻き込みながら、個人や工程別ではなく大衆運動として、人々の思考・行動様式を集団的に変えていくのがベトナム人には向いているようである。この過程を通じて彼らは、自分たちが主人公であること、それに誇りとやりがいを持つこと、むだを排除し効率を追求すること、皆で協力すれば会社はよくなることなどを学ぶ。ミン氏にみせてもらったある教材には、工場から帰る際には道に広がって歩くと邪魔になるので片方によけて歩けという対比写真があった。日本では、大人にこんなことを教える必要はないであろう。
第2に、大事なのは機械でなくヒトであること。ベトナムでなくてもその程度の主張はありそうだが、ここでいうヒトとは従業員およびその家族である。企業のミッションとして、従業員、その家族、会社、顧客、社会の 5つの利益が重要視される。近江商人の三方よしは売り手・買い手・世間の利益の同時追求だが、ここでの五方よしは、従業員とその家族が先に記載される。この点でユニークといえるだろう。
この背景として、次のような事実がある。ベトナムは伝統的に村社会で、村のお祭り・共同作業・結婚式・葬式などにみなが参加し、それを当然と思っているが、企業に来るとなぜかワーカーは個人主義や自分勝手に変貌する。ミン氏はこの文化断絶を是正し、企業においても村と同様のコミュニティー意識を復活させる必要があると説く。そのためには、会社・顧客・社会の利益をいう前に、まず会社に勤めるヒトの団結・向上心・利益を高めることが大切だとする。かつて日本では「会社は家族」といった気運があったが、現在そうした考え方は日本人の若者にはうけいれられない。しかしベトナムでは、企業におけるコミュニティー意識の再生・強化はまだ十分受け入れられる素地が残っているようである。
第3に、すべての従業員によるSxQxCxDxE の強化と実施。S は安全(safety)、Q は品質(quality)、C はコスト削減(cost)、D は納期厳守(delivery)、Eは環境(environment)。Safety やQCD についてはあらためて説明するまでもないだろう。ここでのEは通常の環境保全に加えて、上記のヒト(従業員とその家族)の能力発揮と満足のための環境整備も含まれる。ここにも、ベトナムでは従業員の幸福が大事という思考があらわれている。GKM社は、この 5 要素の積(掛け算)を最大化するように企業を指導し、その達成度を評価する。ここで重要な点は、すべての従業員がこの 5 要素を学んで自分の持ち場で実行すべきこと。生産と品質管理が別部門ではだめだし、安全対策と環境対策の担当が分かれてもだめである。GKM社によれば、従業員の1人1人がSxQxCxDxEに責任を持つ「マネジャー」でなければならない。この方針は、高卒の従業員は容易に受けいれるが、大卒者は学んだ専門分野にこだわり、それのみを担当しようとするから、理解も受容もできずやめていく人が多いという。
GKM 社の最初の指導が終わっても、各企業はこれらの5要素の維持・強化のために社内運動を継続していくことになる。各部署の朝礼で Tam The と SxQxCxDxE を復唱し、学習の場を設け、全社会合を開催し、従業員の家族を呼んで新思考・新行動を学んでもらい家庭でも実行するなど。GKM 社の方法は、5S・カイゼン・QCC といった現場の効率性から入るのではなく、従業員の気持ちや鼓舞を最重要のエントリポイントとする点で日本のやり方とは異なっている。日本や韓国ではそうした精神的側面は自動的にわいてくるかもしれないが、ベトナムではあえて明示的に人々の心を変革するステップが必要であるという。これは、文化的相違を反映するのだろう。5S やカイゼンは彼らも学び、工場はそれなりにきれいだが、整理整頓を完璧に行い、トイレはピカピカでなければならないというほどのこだわりはないように感じられた。
第4 に、以上のベトナム企業の強化を前提として、新たな二国間産業連携の「2.0 モデル」を提唱している。これは日本企業との連携を主な対象とするが、ベトナム企業が韓国、台湾、欧米などの企業と協力する際にも適用されうる。従来の協力(バージョン 1.0)は、日本企業が経営・技術・市場をベトナムに持ち込み、現地の安価で器用な労働を用いて生産するというものであった。この協力はある意味でウィンウィンではあるが、圧倒的な知識と実力をもつ日本が先生、ベトナムが生徒という形になっている。その際には、日本のやり方(経営・技術指導・契約・雇用・会計等々)をそのまま導入してもうまくいかないから、日本モデルをどのように修正すればベトナムの子会社や協力企業の運営が効率的になるかを日本側で考えなければならなかった。これはあくまで日本側の作業であった。これに成功する日本企業もあるし、失敗する企業もある。GKM 社の提唱する二国間産業連携バージョン2.0は、先生・生徒の上下関係ではなく、双方がお互いのよいものを持ち寄って価値を共創する。具体的には、日本側は「生産技術」と「市場」、ベトナム側は「経営技術」と「従業員教育」(GKM社の方法で改善された、やる気と効率性の高い現地企業とその従業員)をもちよる。これをMBV(Made by Vietnam)とMBJ(Made by Japan)の協力とし、両者の結合を二国間産業連携バージョン2.0と呼んでいる。
これが実現すれば、日本企業は現地企業や従業員をどう指導・訓練すればよいかに頭を悩ます必要はなくなる。それはベトナム側の仕事である。GKM 社のやり方は、日本のよいところを学び、それと親和性のある企業文化をベトナム人に適合するやり方(集団志向・コミュニティー主義)で育てるから、日本モデル(5S、カイゼン、QCD、長期志向など)との接合性は確保されている。また、日本経済の弱体化という現実の中で、これまで援助してきた途上国とのより対等な新関係の構築に向けて、1 つの重要なモデルとなりうるであろう。またこれは、日本モデルを修正してベトナムモデルをつくるという翻訳的適応の好例ともなりうるであろう。
展開・拡大のための課題
マインドセット(Tam the)改革、従業員と家族の重視、全社をあげた運動、会社のコミュニティー化、SxQxCxDxEの推進、二国間産業連携の2.0モデル等は、総体として、ベトナム企業のあり方および外国企業との協力のあり方を大変革する可能性を秘めている。これはさらに、中所得の罠の突破、スマイルカーブ上の付加価値拡大、先進国化・高所得化といったベトナムの夢の達成手段の1つになりうる(GKM社のモデルがベトナムに有効であるとの前提で)。残る課題は、①このモデルの有効性の認知度を両国の官民において高めること、②多くのベトナム企業がこの変革に成功し、外国企業との連携可能なパートナーが増えること、③それを理解した日系企業(および他の外国企業)が実際に2.0連携を築いていくこと、であろうと思われる。つまり、外国モデル導入の3ステップでいえば、「学習」と「適応・内部化」の段階が終わり、「普及」に着手せねばならない段階に来ている(菊池剛、「『仲介型』技術移転に関する考察:3段階モデルの構築と適用」、拓殖大学博士学位論文、2014)。

大野健一教授、グエン・ダン・ミン准教授博士、そしてWindtechテクノロジー株式会社の経営陣によるWindtech訪問中の様子。
これまで GKM はさまざまな分野の約千社のベトナム企業を教え、改善してきた。その中で規模が大きく、よく知られた現地企業としては、自動車組立のチュオンハイ(Thaco)社があげられる。同社は自社ブランドの商用車を生産するほか、マツダ・プジョー・BMW・三菱・Kia などの乗用車や商用車を委託組立している。同社の社長や経営陣はミン氏の指導を高く評価している。そのほかVCC(Viettel社の子会社)やPetrolimex社も有名だが、GKM社の関与は短期・部分的にとどまる。このほか、私の知る限り、GKM 社が研修や企業訪問を通じて支援した企業にはLe Group社(金属部品)、Manutronics社(電子部品)、Thieu Do(制服やスーツ)、NCNetwork(日越企業ネットワーク)、AVC クレーン社(工場内クレーン)、Windtech 社(金属フレーム・部品)、AMECC社(大型設備・建物)、Bao Minh 社(菓子)などがある。このほかにも製造業・観光・衣料・医療などさまざまな分野の企業が GKM社の方法に触れ、学んだことであろう。企業経営者向けの CEO コースはすでに何十回と開催されているから、関心と影響は広がり続けている。以前、三菱商事現地社長の舩山徹氏も GKM 社に関心を持ち、同コースに参加した。しかし全体としてみれば、日越の産官学コミュニティーにおけるこの方法の認知度はまだ高くない。
日本の生産性運動は、1950年代後半に多くの企業のニーズ、有能な産業NPOの支援、海外ミッション派遣とその帰国後セミナーなどを通じて、5 年余の間に学習→適応・内部化→普及の段階を通過して全国レベルで大きな成果をあげた。いっぽうGKM社の活動は純粋に民間であり、単独活動で、予算・人員規模も小さく、公的機関や産業NPOの公認や協力はまだ受けていない。
設立10周年を迎え、実績を着実に重ねてきたGKM社は、従来の企業秘密を公開し、宣伝活動に注力する予定である。その内容はだいたいのところ、このメモに書いたものとオーバーラップするはずである。宣伝活動の一環として、10 月には東京・名古屋でセミナー等を実施すると聞いている。方法論の宣伝活動と顧客企業の成功体験が相互に強めあいながら拡大し、ある臨界点を超えれば、ベトナム全土を巻き込む運動になるかもしれない。だが今のところ拡大には、広報資料、宣伝メディア、支援組織、日越の官民による認知などの問題が残されている。まずは、「企業秘密」を効果的に説明する冊子・論文・レポート・プレゼン・ウェブサイト等が必要であろう。
以上、GKM 社によるベトナム企業のレベルアップについてみてきたが、ミン氏は、ベトナムは「企業」「家庭」「政府」の3 つのレベルアップが必要という。GKM 社は前2者には着手済みだが、政府の改善についてはこれまでよいエントリポイントがなかった。だが現在、ト・ラム書記長が率いる党・政府は大胆な改革を行いつつある。行政分野の改革はすでに実施されたが、経済分野でも民間部門開発(PSD)が1 つの柱として打ち出されている。しかしその具体的な方法がわかっていない。ミン氏はGKM社が開発した方法論がそれに貢献できると信じ、党・政府へのアプローチを行っていくつもりであるように、私には思われる。
以上
 日本語
日本語